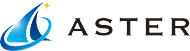お知らせ
事業所報
2025/07/17
![]() Author :下山 和也
Author :下山 和也
THE ASTER TIMES 2025.7 vol.45
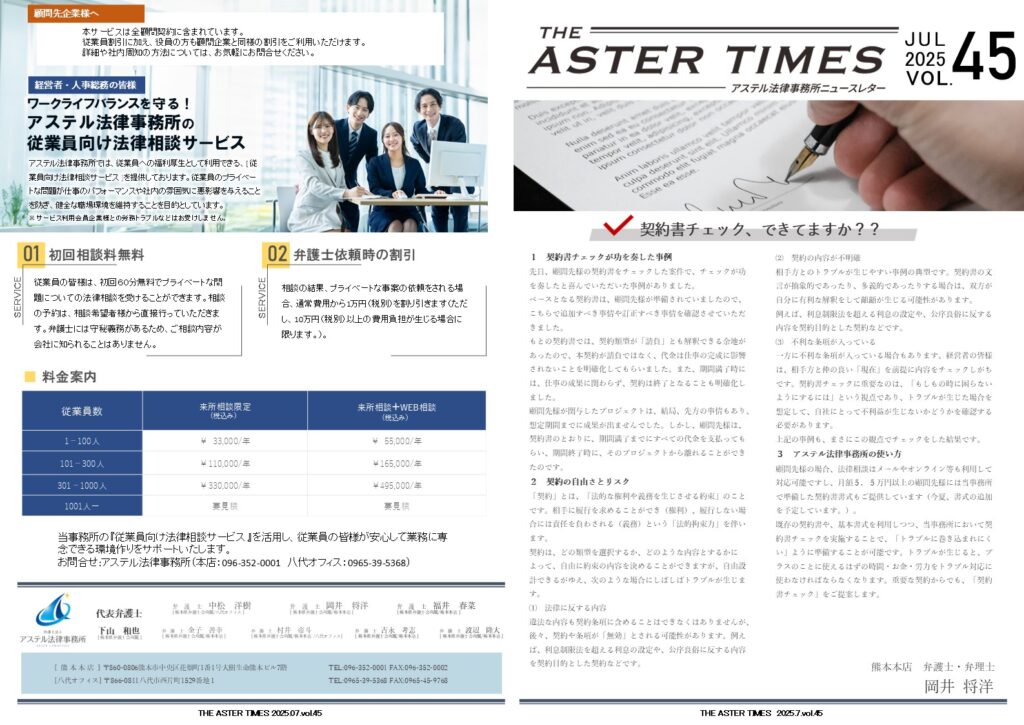 |
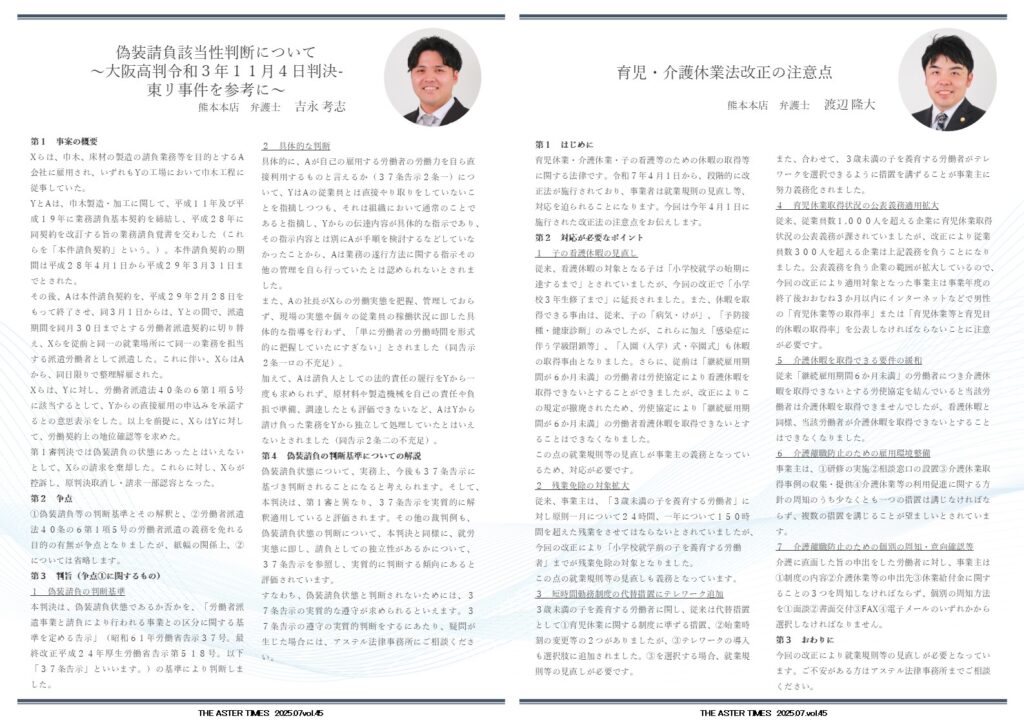 |
契約書チェック、できてますか??
1 契約書チェックが功を奏した事例
先日、顧問先様の契約書をチェックした案件で、チェックが功を奏したと喜んでいただいた事例がありました。
ベースとなる契約書は、顧問先様が準備されていましたので、こちらで追加すべき事情や訂正すべき事情を確認させていただきました。
もとの契約書では、契約類型が「請負」とも解釈できる余地があったので、本契約が請負ではなく、代金は仕事の完成に影響されないことを明確化してもらいました。また、期間満了時には、仕事の成果に関わらず、契約は終了となることも明確化しました。
顧問先様が関与したプロジェクトは、結局、先方の事情もあり、想定期間までに成果が出ませんでした。しかし、顧問先様は、契約書のとおりに、期間満了までにすべての代金を支払ってもらい、期間終了時に、そのプロジェクトから離れることができたのです。
2 契約の自由さとリスク
「契約」とは、「法的な権利や義務を生じさせる約束」のことです。相手に履行を求めることができ(権利)、履行しない場合には責任を負わされる(義務)という「法的拘束力」を伴います。
契約は、どの類型を選択するか、どのような内容とするかによって、自由に約束の内容を決めることができますが、自由設計できるがゆえ、次のような場合にしばしばトラブルが生じます。
⑴ 法律に反する内容
違法な内容も契約条項に含めることはできなくはありませんが、後々、契約や条項が「無効」とされる可能性があります。例えば、利息制限法を超える利息の設定や、公序良俗に反する内容を契約目的とした契約などです。
⑵ 契約の内容が不明確
相手方とのトラブルが生じやすい事例の典型です。契約書の文言が抽象的であったり、多義的であったりする場合は、双方が自分に有利な解釈をして齟齬が生じる可能性があります。
例えば、利息制限法を超える利息の設定や、公序良俗に反する内容を契約目的とした契約などです。
⑶ 不利な条項が入っている
一方に不利な条項が入っている場合もあります。経営者の皆様は、相手方と仲の良い「現在」を前提に内容をチェックしがちです。契約書チェックに重要なのは、「もしもの時に困らないようにするには」という視点であり、トラブルが生じた場合を想定して、自社にとって不利益が生じないかどうかを確認する必要があります。
上記の事例も、まさにこの観点でチェックをした結果です。
3 アステル法律事務所の使い方
顧問先様の場合、法律相談はメールやオンライン等も利用して対応可能ですし、月額5.5万円以上の顧問先様には当事務所で準備した契約書書式もご提供しています(今夏、書式の追加を予定しています。)。
既存の契約書や、基本書式を利用しつつ、当事務所において契約書チェックを実施することで、「トラブルに巻き込まれにくい」ように準備することが可能です。トラブルが生じると、プラスのことに使えるはずの時間・お金・労力をトラブル対応に使わなければならなくなります。重要な契約からでも、「契約書チェック」をご提案します。
熊本本店 弁護士・弁理士 岡井将洋
偽装請負該当性判断について ~大阪高判令和3年11月4日判決-東リ事件を参考に~
第1 事案の概要
Xらは、巾木、床材の製造の請負業務等を目的とするA会社に雇用され、いずれもYの工場において巾木工程に従事していた。
YとAは、巾木製造・加工に関して、平成11年及び平成19年に業務請負基本契約を締結し、平成28年に同契約を改訂する旨の業務請負覚書を交わした(これらを「本件請負契約」という。)。本件請負契約の期間は平成28年4月1日から平成29年3月31日までとされた。
その後、Aは本件請負契約を、平成29年2月28日をもって終了させ、同3月1日からは、Yとの間で、派遣期間を同月30日までとする労働者派遣契約に切り替え、Xらを従前と同一の就業場所にて同一の業務を担当する派遣労働者として派遣した。これに伴い、XらはAから、同日限りで整理解雇された。
Xらは、Yに対し、労働者派遣法40条の6第1項5号に該当するとして、Yからの直接雇用の申込みを承諾するとの意思表示をした。以上を前提に、XらはYに対して、労働契約上の地位確認等を求めた。
第1審判決では偽装請負の状態にあったとはいえないとして、Xらの請求を棄却した。これらに対し、Xらが控訴し、原判決取消し・請求一部認容となった。
第2 争点
①偽装請負等の判断基準とその解釈と、②労働者派遣法40条の6第1項5号の労働者派遣の義務を免れる目的の有無が争点となりましたが、紙幅の関係上、②については省略します。
第3 判旨(争点①に関するもの)
1 偽装請負の判断基準
本判決は、偽装請負状態であるか否かを、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示」(昭和61年労働省告示37号。最終改正平成24年厚生労働省告示第518号。以下「37条告示」といいます。)の基準により判断しました。
2 具体的な判断
具体的に、Aが自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものと言えるか(37条告示2条一)について、YはAの従業員とは直接やり取りをしていないことを指摘しつつも、それは組織において通常のことであると指摘し、Yからの伝達内容が具体的な指示であり、その指示内容とは別にAが手順を検討するなどしていなかったことから、Aは業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行っていたとは認められないとされました。
また、Aの社長がXらの労働実態を把握、管理しておらず、現場の実態や個々の従業員の稼働状況に即した具体的な指導を行わず、「単に労働者の労働時間を形式的に把握していたにすぎない」とされました(同告示2条一ロの不充足)。
加えて、Aは請負人としての法的責任の履行をYから一度も求められず、原材料や製造機械を自己の責任や負担で準備、調達したとも評価できないなど、AはYから請け負った業務をYから独立して処理していたとはいえないとされました(同告示2条二の不充足)。
第4 偽装請負の判断基準についての解説
偽装請負状態について、実務上、今後も37条告示に基づき判断されることになると考えられます。そして、本判決は、第1審と異なり、37条告示を実質的に解釈適用していると評価されます。その他の裁判例も、偽装請負状態の判断について、本判決と同様に、就労実態に即し、請負としての独立性があるかについて、37条告示を参照し、実質的に判断する傾向にあると評価されています。
すなわち、偽装請負状態と判断されないためには、37条告示の実質的な遵守が求められるといえます。37条告示の遵守の実質的判断をするにあたり、疑問が生じた場合には、アステル法律事務所にご相談ください。
熊本本店 弁護士 吉永 考志
育児・介護休業法改正の注意点
第1 はじめに
育児休業・介護休業・子の看護等のための休暇の取得等に関する法律です。令和7年4月1日から、段階的に改正法が施行されており、事業者は就業規則の見直し等、対応を迫られることになります。今回は今年4月1日に施行された改正法の注意点をお伝えします。
第2 対応が必要なポイント
1 子の看護休暇の見直し
従来、看護休暇の対象となる子は「小学校就学の始期に達するまで」とされていましたが、今回の改正で「小学校3年生修了まで」に延長されました。また、休暇を取得できる事由は、従来、子の「病気・けが」、「予防接種・健康診断」のみでしたが、これらに加え「感染症に伴う学級閉鎖等」、「入園(入学)式・卒園式」も休暇の取得事由となりました。さらに、従前は「継続雇用期間が6か月未満」の労働者は労使協定により看護休暇を取得できないとすることができましたが、改正によりこの規定が撤廃されたため、労使協定により「継続雇用期間が6か月未満」の労働者看護休暇を取得できないとすることはできなくなりました。
この点の就業規則等の見直しが事業主の義務となっているため、対応が必要です。
2 残業免除の対象拡大
従来、事業主は、「3歳未満の子を養育する労働者」に対し原則一月について24時間、一年について150時間を超えた残業をさせてはならないとされていましたが、今回の改正により「小学校就学前の子を養育する労働者」までが残業免除の対象となりました。
この点の就業規則等の見直しも義務となっています。
3 短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加
3歳未満の子を養育する労働者に関し、従来は代替措置として①育児休業に関する制度に準ずる措置、②始業時刻の変更等の2つがありましたが、③テレワークの導入も選択肢に追加されました。③を選択する場合、就業規則等の見直しが必要です。
また、合わせて、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが事業主に努力義務化されました。
4 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
従来、従業員数1,000人を超える企業に育児休業取得状況の公表義務が課されていましたが、改正により従業員数300人を超える企業は上記義務を負うことになりました。公表義務を負う企業の範囲が拡大しているので、今回の改正により適用対象となった事業主は事業年度の終了後おおむね3か月以内にインターネットなどで男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を公表しなければならないことに注意が必要です。
5 介護休暇を取得できる要件の緩和
従来「継続雇用期間6か月未満」の労働者につき介護休暇を取得できないとする労使協定を結んでいると当該労働者は介護休暇を取得できませんでしたが、看護休暇と同様、当該労働者が介護休暇を取得できないとすることはできなくなりました。
6 介護離職防止のための雇用環境整備
事業主は、①研修の実施②相談窓口の設置③介護休業取得事例の収集・提供④介護休業等の利用促進に関する方針の周知のうち少なくとも一つの措置は講じなければならず、複数の措置を講じることが望ましいとされています。
7 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申出をした労働者に対し、事業主は①制度の内容②介護休業等の申出先③休業給付金に関することの3つを周知しなければならず、個別の周知方法を①面談②書面交付③FAX④電子メールのいずれかから選択しなければなりません。
第3 おわりに
今回の改正により就業規則等の見直しが必要となっています。ご不安がある方はアステル法律事務所までご相談ください。
Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約
法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!
tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!
tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!
受付時間/平日9:00〜17:00