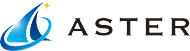トピックス
2023/08/16 破産トピックス 破産手続総論
自己破産のメリット
破産を検討しようとしている方の中には、既に、予定の返済ができていなかったり返済のために借金をしたりする状況になっているケースが少なくありません。そういった場合、返済のために過酷な節約を余儀なくされていたり、債権者から郵便や電話の督促を受けていたりと、生活が行き詰まっていることも往々にしてあります。
そういった方には、破産手続をとり、経済生活の再生を図ることをおすすめしています。
今回は、破産手続をとることによるメリットについて、ご説明します。
(1)破産手続の概要
破産手続の概要については、こちらの記事をご覧ください。
破産手続では、経済的に破綻した債務者の財産の整理と、換価等による債権者への配当を行うことになります。
(2)債権者からの督促、取立ての停止
貸金業者、債権回収会社の督促、取立方法には、法令による制限があります。
債務者が、債務の処理を弁護士に依頼したり裁判所で手続をとったりして、その旨が書面で通知された場合には、原則として、債務者本人への連絡や取立ては禁止されます。
債権者からの督促に疲弊している方は、弁護士の受任通知により連絡が止まることになりますので、
(3)生計の建て直し
債権者の督促、取立てが禁止される結果、受任通知後は、今まで返済に充てていた金銭を生計にあてることができるようになります。
また、破産手続開始決定時の財産は、破産手続の中で破産管財人が管理し債権者への配当を目指すことになりますが、破産手続開始決定後に新たに得た給与等の財産は、その全額を破産者が使うことができます。
(4)民事訴訟、保全、強制執行手続の中断
破産手続開始決定があると、破産財団の管理処分権限が破産管財人に専属し(破産法第78条1項)、債権者が破産手続によらずにその債権を行使することは禁止されます(破産法第100条)。
そのため、破産手続開始決定後は、破産財団に対する強制執行、保全等はできなくなり(破産法第42条1項)、既になされたこれらの手続も効力を失います(同条2項本文)。また、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は中断します(破産法第44条1項)。
既に支払不能状態にあり、債権者から強制執行、保全等の手続をとられてしまった方は、早急に破産申立てを行う必要があるといえます。
(5)免責
破産者が個人である場合、免責不許可事由がないかぎり(破産法第252条1項)、破産と併せて免責許可を申し立てて債務の弁済義務を免れる、つまり、裁判所の許可を得て、残りの借金を法律上返済しなくてよいものとしてもらうことができます。
ただし、税金、婚姻費用・養育費、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権等、一部の債権については、その性質上、返済義務がなくならないものとされています(破産法第253条1項)。
多重債務者の方の中には、インターネット等で検索し、破産に対して過度にネガティブなイメージを持っていたり、免責不許可事由があるから破産しても意味がないと思っていたりする方がいますが、実務とは大きく異なることも珍しくありません。
経済生活建て直しのために、どのような手段をとるべきなのか、アステル法律事務所にご相談ください。
Contact usお問い合わせ・法律相談のご予約
法的な問題でお困りの方は
まずは弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください!
tel.0120-94くよくよ-74なし55GO! GO!
tel.0120-94-7455くよくよなしGO! GO!
受付時間/平日9:00〜17:00